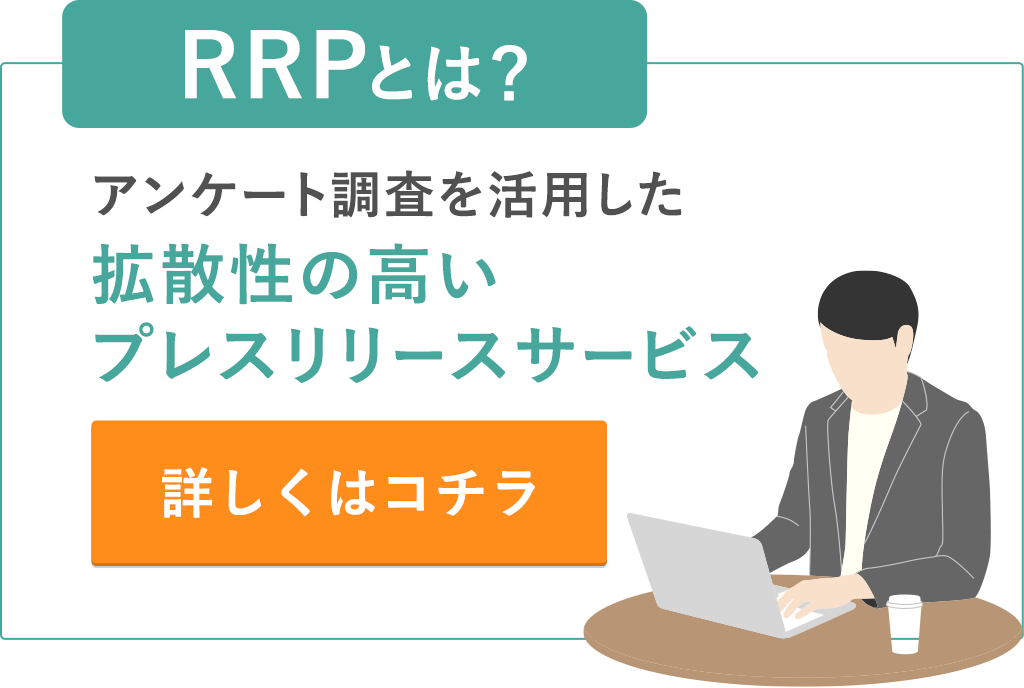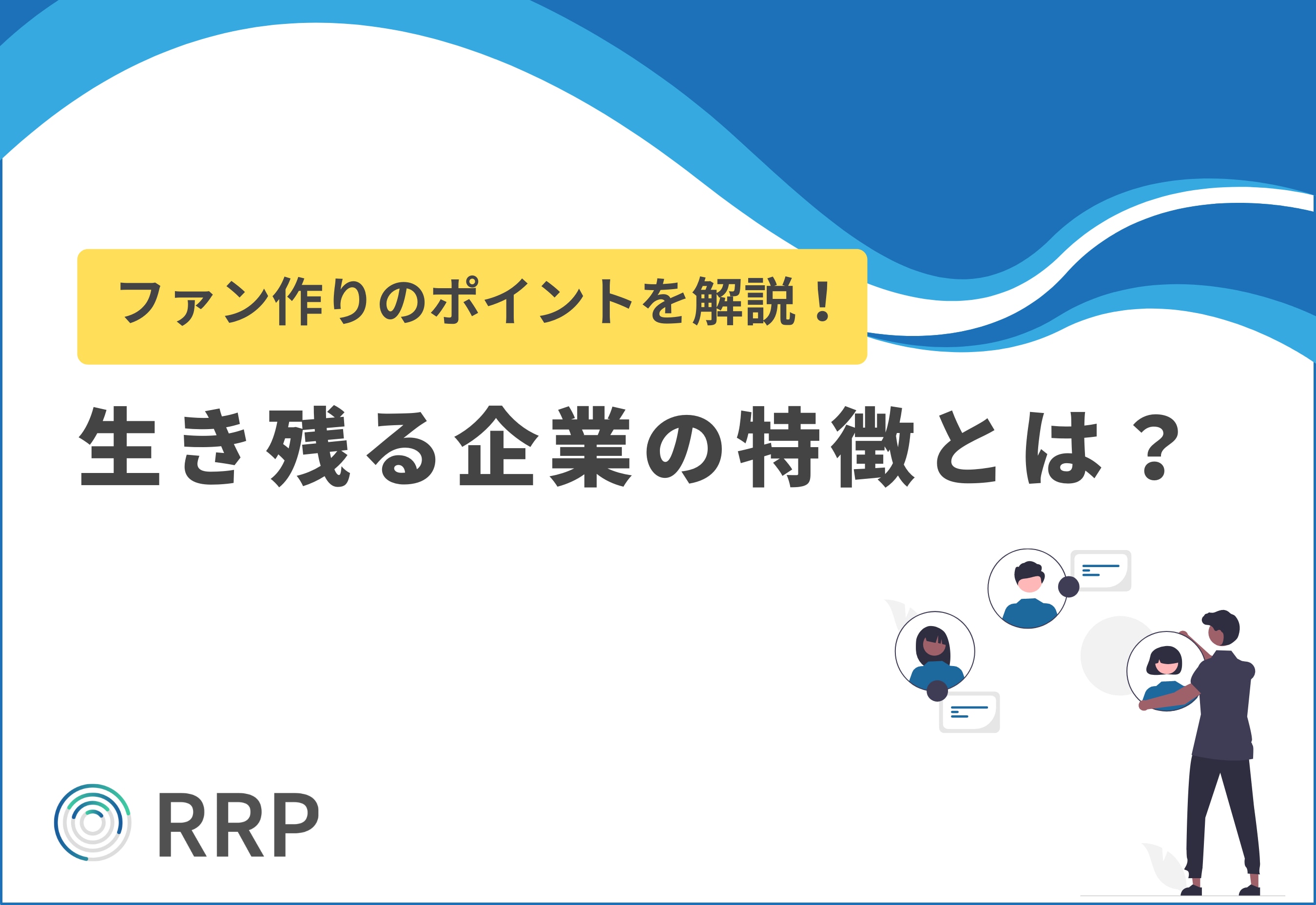
生き残る企業の特徴とは?ファン作りのポイントを解説!
現代は、いろいろなビジネスにおいて商品の質や機能で大きく差別化をすることが困難になりました。さまざまな背景から、新規顧客の獲得がより難しくなっていくと言われています。
これからの時代で市場に根強く生き残っていくためには、既存顧客を長期的に支持してくれるファンにすること、つまりファン化することが大切なのです。
そこで今回は、ファン化についてやリピーターとの違い、ファン作りがもたらすメリットなどをご紹介します。
ファン作りとは何か知りたい方はもちろん、自社商品やサービスのファンを増やしたい・手法を知りたい方や、問い合わせ数・売り上げを増やしていきたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。
目次[非表示]
- 1.ファン化とは?
- 2.リピーターとの違いとは?
- 3.ファン作りの重要性
- 4.ファン作りがもたらすメリット
- 4.1.口コミで商品の良さを広めてくれる
- 4.2.リピート購入につながる
- 4.3.購入単価の向上が期待できる
- 4.4.スペック競争・価格競争を回避しやすい
- 4.5.リアルな顧客の意見を聞くことができる
- 5.ファン作りのフロー
- 6.ファン作りのポイント
- 6.1.顧客満足度を上げる
- 6.2.アンバサダー施策を取り入れる
- 6.3.共感される仕組みをつくる
- 7.ファン作りに成功した企業例
- 7.1.事例①:コクヨ
- 7.2.事例②:マナラ化粧品(株式会社ランクアップ)
- 7.3.事例③:サッポロポテト(カルビー株式会社)
- 8.まとめ
ファン化とは?

ファン化とは、既存の顧客を、よりエンゲージメント(つながりの度合い)の高い顧客=ファンを育てることを指します。
一般的に指す顧客とファンとの違いは、ファンは「応援する気持ち」があることでしょう。一般的な顧客は、商品やサービスをただ使っているだけで、より安くスペックの高い商品・サービスがあると、そちらを使用する可能性が高いです。
しかし、ファンはその商品・サービスを愛好し、応援しているので、ほかにどんなに良い商品・サービスがあったとしても、移行したりせず、長くその商品・サービスを使い続けるのです。
リピーターとの違いとは?
では、ファンとリピーターにはどのような違いがあるのでしょうか。
たとえば、家の近所にコンビニがあったとして、何度も利用する人はリピーターにあたります。
しかし、そのコンビニに特別な思い入れはなく、もっと近所にほかのコンビニができるとそちらを利用するでしょう。
このように、リピーターの背景には競合の存在や立地などの環境要因が大きく関係します。それらを総合して利用頻度を分析する概念こそがリピーターなのです。
このリピーターに対して、ファンは顧客の思い入れの状態に注目します。
ファンは、同じ購入ならこの店から、この商品やブランドから買えば間違いないといったマインドを持っているのです。
そのため、ファンは市場環境の変化にあまり影響を受けないでしょう。
ファンとリピーターの違いは、能動的に選んでくれるか、顧客の状態を定性的に見る指標だという事なのです。
ファン作りの重要性
ビジネスの現場では、売上高の8割が既存顧客の2割が占めています。
今後の企業活動には、LTVを高めることによって売上を伸ばしていく戦略が必要です。
顧客の思い入れの度合いは何かで測るのが難しいものですから、数値化して売り上げ計画と直結させる作業にはあまり向いていないでしょう。
しかし、ファン作りの視点は、経営の視点から見ても非常に重要です。
事業モデルがBtoBであれ、BtoCであれ、顧客に能動的に選んでもらう存在になるには、まずはできるだけ顧客に対して貢献することが基本となるでしょう。
ファン作りがもたらすメリット

次に、ファン作りがもたらすメリットをご紹介します。ファンを作ることで、いろいろなメリットが生まれるのです。
口コミで商品の良さを広めてくれる
ファンは、SNSや口コミで商品やサービスの情報を発信してくれます。人は、自分が強く良いと思うものについて、周りの人たちに「紹介したい、みんなに話したい」といった心理が生まれます。
その一方で、「友達のように近い関係の人からの紹介・口コミは信頼できる」と考えている人も少なくありません。
個人の口コミがSNSやインターネットサイトなどで広く拡散される現代では、一人のファンから高く評価されることは、数多くの新しいファンをつくる可能性を持つのです。
リピート購入につながる
ファンは、商品やサービスをリピート購入してくれます。
商品やサービスをリピート購入してくれる人が増加すると、企業側は売上の予想が立てやすく、事業の安定性が増すでしょう。
また、新規顧客への販売コストは、既存顧客への販売コストに比べて5倍程度のコストがかかるとされています。そのため、リピート購入を増やすことは、新規の営業や新商品開発などにかかるコストを減らしてくれるのです。
購入単価の向上が期待できる
特定の商品やサービスのファンになると、同じブランドの商品や、それに関連する他の商品の情報にも興味・関心を持ちやすくなります。
今まで手にすることがなかった高単価の商品に注目したり、購入したりする確率が高まる可能性があります。
スペック競争・価格競争を回避しやすい
ファンはその商品・サービスを愛用し、応援しているので、スペックや価格の多少の変動について左右されにくい傾向があります。
そのため、根強いファン層を持った商品やサービスは、競合他社との細かいスペック競争やシビアな価格競争に巻き込まれるリスクが比較的低いでしょう。
リアルな顧客の意見を聞くことができる
商品やサービスを利用した顧客からの感想や要望などは、企業にとって価値のある重要な情報です。
ファンがいると、リアルな意見や要望、感想などを直接聞くことができる可能性もあります。
このような情報は、企業のこれからにとっても大切な価値となります。
ファン作りのフロー

では、ファンはどうやって作っていけばよいのでしょうか。
ファンはすぐに生まれるわけではありません。いくつかの段階を踏み、最終的にファンにつながることが多いのです。
ここからは、ファン作りの基本的なフローをご紹介します。
1.見込み顧客
見込み顧客とは、企業が発信する情報に定期的にリアクションしてくれる人を指します。
購入には至っていないがSNSやメルマガなどに登録している方や資料請求・ホームページからお問い合わせをくれる方、SNSでよくコメントをくれる方などを指します。
2.顧客
顧客は実際に、商品やサービスを購入してくれた人を指します。
一度商品やサービスを利用してくれた方を指し、顧客からファン化するためには、期待値を上回ることを目指し、口コミを発生させる仕掛けを構築するのです。
3.ファン
ファンとは、2回目以上の来店や、新しい顧客を紹介してくれるような人を指します。期待値を上回るサービスの提供や、商品に興味を持った方が、リピートしてくれて口コミを起こしてくれるファンになってくれるのです。
顧客よりも一歩踏み込んだ深いコミュニケーションを取ることによって、特別感を感じ、ファン化の定着につながるでしょう。
ファン作りのポイント

では、ファンを実際に作るにはどんなポイントがあるのでしょうか。
顧客満足度を上げる
前提として、顧客がどのようなニーズを持っているのかを把握することが大切です。
顧客の期待を超える、より良い商品やサービス、質の高い対応をすることによって、満足度を上げることができます。
想定している顧客が商品やサービスに期待していることは何でしょうか。店舗の雰囲気や店員の接客態度など、どのように受け取られているのでしょうか。
日々集まってくる販売データやアンケート、カスタマーサポートで受ける生の声、接客などから、顧客ニーズをしっかり把握することが重要です。そして、顧客の期待を上回る、より良い商品やサービス、質の高い対応をすることにより、顧客の満足度を向上させることができるのです。
アンバサダー施策を取り入れる
アンバサダーとは、日本語で「大使」などという意味を持ちます。ファン自らに商品やサービスの情報発信をしてもらい、その代わりにアンバサダー限定の商品をプレゼントしたり、商品をお得に提供したりするのが、アンバサダー施策の一例です。
また、アンバサダーによるSNS投稿を、自社サイトで紹介するのも良いでしょう。
共感される仕組みをつくる
ファン作りには、顧客の心に寄り添って、共感される仕組みをつくることも大切です。
SNSやイベントなどを通じて、企業と顧客との距離を近づける取り組みも効果的です。
たとえば、顧客の声をもとに新商品を開発するといった企画の場合は、商品づくりのストーリーに関わった顧客は、ただの消費者ではなく、自分も作り手側の一員としてその商品に関与している気持ちになるでしょう。
自分がこんな商品・サービスを支えているといった意識が、強いファン化につながります。
また、環境保護や社会課題、SDGsなどへの取り組みなど、企業のメッセージや社会活動のスタンスに共感することにより、企業や商品の熱狂的なファンになることもあるのです。
ファン作りに成功した企業例
では、最後にファン作りに成功した企業の例を見ていきましょう。
どのような企業がファン作りに成功したのでしょうか。
皆さんが知っている企業も多いかもしれません。
事例①:コクヨ
引用:コクヨ
コクヨは、SNSをうまく利用したファン作りに成功した企業です。
Instagramで10万人以上ものフォロワーがいるコクヨは、動画をうまく活用することによって、無機質な文房具の魅力を伝えることに成功したのです。
テキストや画像だけでは伝わらないような使用感や、細かい情報を動画でユーザーに疑似体験させて効果的に伝えているのです。
商品の紹介や魅力を画像・テキスト・動画を組み合わせてわかりやすく伝えることにより、ユーザーにも見やすくファンになりやすいでしょう。それが、商品購買につながっています。
ただインパクトのある動画だけでなく、シンプルに伝わりやすい動画制作をしているといった点も文房具ならではの良さを活かしていて、より効果的なマーケティングにつながったのです。
事例②:マナラ化粧品(株式会社ランクアップ)
株式会社ランクアップは、マナラ化粧品などスキンケア商品を中心としたコスメ商品の開発や販売を行っています。特に、マナラ化粧品はファンとの直接交流を持ったイベント運営に力を入れています。
1年間で1000人とのファンと会うことを目的にしたファンミーティングでは、全国各地で規模さまざまなイベントを実施し、ファンとの交流を増やしました。このようなイベントは、たくさんのファンの声を聴くことや、ファンに対してブランド・商品の理解を深めてもらうことを目的にしています。
ポイントとなるのは、定量的な目標を決めてファンミーティング施策に取り組むことや、どうしてファンを作ることが大切なのかを定義してイベントを運営すること、イベントに参加できないファンに対するフォロー施策にも着手したという点です。
事例③:サッポロポテト(カルビー株式会社)
引用:サッポロポテト(カルビー株式会社)
サッポロポテトは、キャンペーンと投稿をうまく使い分けたダブルのコミュニケーションで成功しました。
Twitterは、拡散性や即時性に優れたプラットフォームであるので、SNSの中でもリツイートキャンペーンやハッシュタグ投稿キャンペーンなどキャンペーンでの活用が盛んになっています。
また、キャンペーンと投稿をうまく組み合わせることで、効率的に消費者との接点を増やし、その上でコミュニケーションを活性化させることができるのです。カルビー株式会社が販売しているサッポロポテト公式Twitterアカウントも、この使い分けを効率よく行っているアカウントなのです。
ポイントは、Twitterキャンペーンで確実に接点を創出したことやフォロワーが楽しめるようなOrganic系の投稿でエンゲージメントを高めたことなどでしょう。
まとめ
顧客をファンに育てていくファンマーケティングを行えば、新規顧客の獲得や長期的な利益の安定化につながります。
SNS・プレスリリースなど活用してさまざまな工夫を行いながら、熱狂的なファンを育てて、自社商品・サービスの認知度向上、売上の拡大を目指しましょう。
==============================================================
「RRP」は、大手リサーチ企業によるアンケート調査結果を活用した、訴求力と拡散力のあるプレスリリース配信代行サービスです。
取引社数300社以上、PRTIMES配信数1,000件以上、人気テレビ番組や新聞での掲載など数多くの実績がございます。テーマ選定から記事の執筆など全て経験豊富な専門スタッフが対応!
内容をご確認頂くだけで貴社サービスの認知・売上の向上をサポートします!
ご興味のある方はぜひ下記詳細資料をDLください!